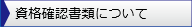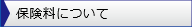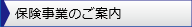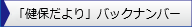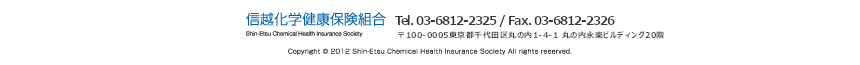HOME > �a�C��P�K�������Ƃ�
HOME > �a�C��P�K�������Ƃ�
�a�C��P�K�������Ƃ�
���N�ی��g���̉����҂��a�C��P�K�������Ƃ��́A��Ë@�ւ̑����փ}�C�i�ی��ؓ�����A����������Ô��1�`3�����ꕔ���S���Ƃ��ĕ��S���A��Â��܂��B�܂��A��Ô���z�ɂȂ����Ƃ��◧�֕����������Ƃ��ȂǁA���܂��܂ȃV�[���ŋ��t���邱�Ƃ��ł��܂��B���t����������́A�i1�j�Ɩ��O�̕a�C��P�K�ł��邱�Ɓi2�j�ی���Ë@�ւɂ����邱�Ɓi3�j�}�C�i�ی��⎑�i�m�F���𑋌��ɒ��邱�Ƃł��B
�N��ʂɌ��鎩�ȕ��S�Ƌ��t����
��Ë@�ւ̑����ŕ��S����ꕔ���S���̕��S�����́A�N��ɂ���ĈقȂ�܂��B
| ���ȕ��S���� | �ی����t���� | |
|---|---|---|
| ���w�Z���w�O | 2�� | 8�� |
| ���w�Z���w��`69�� | 3�� | 7�� |
| 70�`74��(�����) | ||
| ��� | 2�� | 8�� |
| ������݂̏����� | 3�� | 7�� |
- ��70�`74�́u������݂̏����ҁv�Ƃ́A�W����V���z28���~�ȏ�̐l�Ƃ��̔�}�{�҂��Y�����܂��B�������A���ɊY������ꍇ�́A�u��ʁv�����ƂȂ�܂��B
- 70�Έȏ�̔�}�{�҂����Ȃ��l�ŔN��383���~�����̏ꍇ
- 70�Έȏ�̔�}�{�ҁE����}�{�ҁi�������҈�Ð��x�̔�ی��҂ƂȂ��Ă���5�N�ȓ��̐l�j������l�ŁA���v�N���z��520���~�����̐l�́A���N�ی��g���ɐ\�����邱�ƂŁA�u��ʁv�����ɂȂ�܂��B
���ȕ��S�����z�ɂȂ����Ƃ�
��Ô�̎��ȕ��S�ɂ́u���x�z�v���݂����Ă��āA���̊�Ɋ�Â��Čv�Z�������ȕ��S�z�����x�z����ꍇ�A�������z���u���z�×{��v�Ƃ��Ďx������܂��B
���N�ی����g���A��Ô�̕��S���ꕔ�ōςނƂ͂����A�d���a�C�ɂ���������A�������@�����肷��A���z�̈�Ô���x����Ȃ���Ȃ�܂���B���̂悤�ȕ��S���y�����邽�߂ɁA�����҂��P�l�P�P���A����̈�Ë@�ւŎ��ȕ��S�����z�����ȕ��S���x�z�����Ƃ��A���̒������z�����N�ی��g������x������܂��B
��Ô�̎��ȕ��S���v�Z����Ƃ��̊
�a�@�E�f�Ï����ƂɌv�Z
�����̕a�@��f�Ï��ɓ����ɂ������Ă���ꍇ�́A���ꂼ��ʌɌv�Z����܂��B��x�މ@�������ƂɁA�����Ƃ���֍ē��@����Ȃǂ̏ꍇ�́A���ꌎ���ł�����킹��1���̐f�ÂƂ��Čv�Z����܂��B
���Ȃ͕ʂɌv�Z
�����a�@�E�f�Ï����Ɏ��Ȃ�����A�����Ɏ�f����ꍇ�ł��A���ꂼ��ʌɌv�Z����܂��B
���@�ƒʉ@�͕ʂɌv�Z
�����a�@�E�f�Ï��ł��A���@�ƒʉ@�͂��ꂼ��ʌɌv�Z����܂��B
���@���Ɏx�����W�����S�z�͑ΏۊO
���@���Ɋ��҂����S����H��⋏�Z��͌v�Z�̑ΏۊO�ł��B
���z�x�b�h��Ȃǂ͑ΏۊO
�ی��f�Â̑ΏۂƂȂ�Ȃ��A���@�����Ƃ��̍��z�x�b�h���l�œ��ʂɕt�����Ō��p�Ȃǂ͌v�Z�ΏۊO�ł��B
���ȕ��S���x�z�̌v�Z
���ȕ��S���x�z�́A�����ɉ����ĈقȂ�A���̏���������ƈ�ʂ������z�ɐݒ肳��A�s�������Ŕ�ېŎ҂͈�ʂ���z�ɐݒ肳��܂��B�܂�70�Έȏ��70�Ζ����ł͎��ȕ��S���x�z���قȂ�܂��B
�P����������̎��ȕ��S���x�z�i70�Ζ����j
| �����敪 | ���ȕ��S���x�z |
|---|---|
| �@�敪�A(�W����V���z83���~�ȏ�̕�) | 252,600�~�{�i����Ô�|842,000�~�j�~1�� |
| �A�敪�C(�W����V���z53���`79���~�̕�) | 167,400�~�{�i����Ô�|558,000�~�j�~1�� |
| �B�敪�E(�W����V���z28���`50���~�̕�) | 80,100�~�{�i����Ô�|267,000�~�j�~1�� |
| �C�敪�G(�W����V���z26���~�ȉ��̕�) | 57,600�~ |
| �D�敪�I(�s�撬�����Ŕ�ېŎғ�) | 35,400�~ |
�P����������̎��ȕ��S���x�z�i70�Έȏ�74�Έȉ��j
| �敪 |
���ȕ��S���x�z �l�P�ʁi�O���̂݁j |
���ȕ��S���x�z ���ђP�ʁi�O���E���@�j |
|---|---|---|
| ������݇V�@�@�W����V���z83���~�ȏ� |
252,600�~�{�i�����|842,000�~�j�~1�� [�����Y���@140,100�~] |
|
| ������݇U�@�@�W����V���z53���`79���~ |
167,400�~�{�i�����|558,000�~�j�~1�� [�����Y���@93,000�~] |
|
| ������݇T�@�@�W����V���z28���`50���~ |
80,100�~�{�i�����|267,000�~�j�~1�� [�����Y���@44,400�~] |
|
| ��@�@�@�� | 18,000�~ �@�@�N�ԏ���@144,000�~ |
57,600�~ [�����Y���@44,400�~] |
| �Ꮚ���U�i��1�j | 8,000�~ | 24,600�~ |
| �Ꮚ��I�i��2�j | 15,000�~ | |
�i��2�j70�Έȏ�̎҂ŁA���ёS�����s�������Ŕ�ېŎ҂ŏ���������i�N������80���~�ȉ����j�����l��
��70�Έȏ�̊O���×{�ɂ�����N�Ԃ̍��z�×{��@
����i�V���R�P���j���_�̏����敪���u��ʏ����敪�v�܂��́u�Ꮚ���敪�v�ɊY������ꍇ�́A�v�Z���ԁi����̑O�N�W���P���`�V���R�P���j�̂����A��ʏ����敪�܂��͒Ꮚ���敪�ł��������̊O���×{�̎��ȕ��S�z�̍��v��144,000�~�����z�������߂���܂��B
���x�z�K�p�F��ɂ���
���ꌎ�E�����Ë@�ւɂ��������Ƃ��̈�Ô���ȕ��S���x�z����ꍇ�A���N�ی��g�����玖�O�Ɂu���x�z�K�p�F��v�̌�t���A��Ë@�ւ̑����ɒ��邱�ƂŁA���S�����x�z�܂łɗ}���邱�Ƃ��ł��܂��B
���x�z�K�p�F��i�ȉ��A�F��j�̌�t���獂�z�×{��u�������t�v�����܂ł̗���

�K�v�ȓ͏o
�}�C�i�ی��𗘗p����A���O�̎葱���Ȃ��A�x���������z�×{��x�ɂ�������x�z�܂łƂȂ�܂��B�}�C�i�ی������Ђ����p���������B
�u���x�z�K�p�F��\�����v���o �\����
��70�Έȏ�74�Έȉ��̕��Ō��x�z�̓K�p����ꍇ�A�����敪���u�������I�E�U�v�̕��̂ݐ\�����K�v�ł��B
���ȕ��S������Ɍy�������ꍇ
�u���Z���z�×{��v
���т��Ƃ̎��ȕ��S�����z�ɂȂ����Ƃ��i���э��Z�j
���z�×{��́A1����1�����Ƃ̎��ȕ��S�����x�z���Ă���Ƃ��Ɏx���ΏۂƂȂ���̂ł����A���ꐢ�ѓ��ň��z�����Ô�̎��ȕ��S���������������ꍇ�́A���ȕ��S�z�𐢑э��Z���A���̊z��1�����̎��ȕ��S���x�z����ꍇ�ɂ́A�������z���u���Z���z�×{��v�Ƃ��Ďx������܂��B
- ���x���̏���
- ���ꌎ�ɓ��ꐢ�ѓ���21,000�~�ȏ�̎��ȕ��S��2���ȏ゠��ꍇ�ŁA�����̎��ȕ��S�����Z�����z�����ȕ��S���x�z����ꍇ�Ɏx������܂��B
�u���Z���z�×{��v
���z�×{��ɑ�����Y������Ƃ��i�����Y���j
����12�����̊ԂɁA���ꐢ�т�4��ȏ㍂�z�×{��ɊY�������ꍇ�́A4��ڂ��玩�ȕ��S���x�z���ጸ����܂��B
�P����������̎��ȕ��S���x�z�i�����Y���̏ꍇ�j
| �����敪 | ���ȕ��S���x�z |
|---|---|
| �@�敪�A�i�W����V���z83���~�ȏ�̕��j | 140,100�~ |
| �A�敪�C�i�W����V���z53���`79���~�̕��j | 93,000�~ |
| �B�敪�E�i�W����V���z28���`50���~�̕��j | 44,400�~ |
| �C�敪�G�i�W����V���z26���~�ȉ��̕��j | 44,400�~ |
| �D�敪�I�i�s�撬�����Ŕ�ېŎғ��j | 24,600�~ |
���莾�a�ɊY������Ƃ�
����̒������z���a�̎��Â���ꍇ�A�u���莾�a�×{��Ïv�����ƁA���ȕ��S��1����10,000�~�ƂȂ�܂��B�������A�l�H���͂�v���銳�҂�70�Ζ����ŕW����V���z��53���~�ȏ�ɊY������ꍇ�́A���ȕ��S��20,000�~�ɂȂ�܂��B
���Y��������莾�a
���F�a�A�R�E�C���X�܂𓊗^���Ă����V���Ɖu�s�S�nj�Q�A�l�H���͂�v���銳��
�K�v�ȓ͏o
�u���N�ی����莾�a�F��\�����v���o�@�\����
�M�z���w���N�ی��g���̕t�����t
�����N�ی��g���ł́A���ȕ��S�z������Ɍy�������悤�ɁA���ȕ��S������Ô���̊z�����ꍇ�A��ی��҂́u�ꕔ���S�Ҍ����v�Ƃ��āA��}�{�҂́u�Ƒ��×{��t�����v�Ƃ��ĕt�����t���x�����Ă��܂��B�܂����Z���z�×{��ɂ��Ă��A���z���������u���Z���z�×{��t�����v�Ƃ��Ďx�����s���Ă��܂��B
�ꕔ���S�Ҍ���
��ی��҂�����̈�Ë@�ցi�����a�@�͓���̐f�Éȁj�łP�����Ɏx�������A���ȕ��S���̈�Ô��i���z�×{��������āj20,000�~�������������z���x������܂��B�������Z�o�����z��1,000�~�����̏ꍇ�͎x������܂���B�܂�100�~�����̒[���͐�̂Ă���܂��B
�Ƒ��×{��t����
��}�{�҂�����̈�Ë@�ցi�����a�@�͓���̐f�Éȁj�łP�����Ɏx�������A���ȕ��S���̈�Ô��i���z�×{��������āj20,000�~�������������z���x������܂��B�������Z�o�����z��1,000�~�����̏ꍇ�͎x������܂���B�܂�100�~�����̒[���͐�̂Ă���܂��B
���Z���z�×{��t����
���Z���z�×{��x�������ꍇ�ɁA���t�̑ΏۂƂȂ������ȕ��S�̍��v�z����A���Z���z�×{��Ƃ��Ďx�����ꂽ���ƁA1��������20,000�~�������������z���x������܂��B�������A�Z�o�����z��1,000�~�����̏ꍇ�͎x������܂���B�܂�100�~�����̒[���͐�̂Ă���܂��B
- �v�Z�̑ΏۂƂȂ鎩�ȕ��S�z�́A���̏������疖���܂ł�1�����ԁA����̈�Ë@�ւɎx���������ȕ��S�z�ƂȂ�܂��B
- ���@���̐H���×{�E�����×{�ɂ�����W�����S�z�A�܂��͕ی��K�p�O�̃T�[�r�X�ɂ������p�Ȃǂ͎��ȕ��S�z���珜����܂��B
- ���z�×{���Ƃ��Ďx�����ꂽ�z�́A���ȕ��S�z���珜����܂��B
���đւ������������Ƃ�
���N�ی��ł́A��ނȂ�����Ō��N�ی��ł̐f�Â����Ȃ������Ƃ��́A�Ƃ肠������Ô�̑S�z����Ë@�ւɎx�����A�ォ�狋�t���̕����߂�������ꍇ������܂��B���̂悤�����đւ������ɑ��čs���鋋�t���u�×{��v(��}�{�҂̏ꍇ�́u�Ƒ��×{��v)�Ƃ����܂��B
���̏ꍇ�A�x��������p�̂��ׂĂ����t�ΏۂɂȂ�Ƃ͌���܂���B���N�ی��ŔF�߂��Ă��鎡�Õ��@�Ɨ����Ɋ�Â��ĎZ�o���ꂽ�z���x������܂��B
| ��ȓ��e | �K�v�ȏ��� |
|---|---|
| ��ނ��}�C�i�ی��ؓ���ł��Ȃ������Ƃ��� �ی���ȊO�̈�Ë@�ւɂ��������Ƃ� |
|
| �R���Z�b�g�A�e�����߁A�����㎋�̎��×p�ዾ���� ���×p����������Ƃ� |
�@�i�����ዾ���̖��́A��ދy�т��̓���ʂ̉��i���L�ڂ��ꂽ���́j �@�ዾ���쐬�w���� |
| ���{���O�Ŏ�f�����Ƃ� �����{�����Őf�Â����ꍇ�Ɍ��N�ی��̓K�p�����鎡�Â� �����A���ÖړI�ŊC�O�֓n�q�����ꍇ�Ȃǂ͎x���ΏۊO�ƂȂ�܂� |
�@���Ȑf�Ó��e���� |
| ��t�̓��ӂāA�͂�E���イ�E�}�b�T�[�W�̎{�p �����Ƃ� |
|
| �����t�̗A�������Ƃ� |
-
�����@�E�ڍ��@�ȂǏ_�������t�Ŏ{�p����Ƃ����A�{���͗��đւ������̈����ɂȂ�܂��B��������̈ϔC�̋��������ł���_�������t�ɂ��ẮA�_�������t�������߂��̐������s�����Ƃ��F�߂��邽�߁A��Ë@�ւɂ�����̂Ɠ����悤�ɁA�}�C�i�ی��ؓ������A���ȕ��S�݂̂̎x�����Ŏ{�p�����܂��B
- ���N�ی����K�p�����̂́A���܁A�E�P�A�Ŗo�A�P���A���Ȃ�Ɋւ���{�p�ł��B�܂��A���܂�E�P�ɂ��ẮA���}�蓖�̏ꍇ��������t�̓��ӂ��K�v�ł��B
�� ��L�{�p�ł����Ă��ɂ�莩��ƂȂ�i���N�ی����K�p����Ȃ��j�ꍇ������܂��B�ڂ����͂����� - �_�������t�������߂��̐��������邽�߂ɁA�K���������ɗ��p�҂̏������K�v�ɂȂ�܂��B���̍ہA������Ɛ������̓��e���m�F���������ŏ�������悤�ɂ��Ă��������B