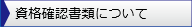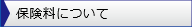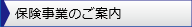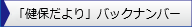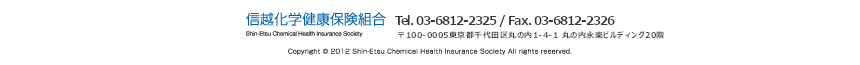HOME > 子どもが生まれたとき
HOME > 子どもが生まれたとき
子どもが生まれたとき
女性被保険者が出産したときは「出産育児一時金」と「出産手当金」が、被扶養者が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。健康保険でいう出産とは、妊娠4カ月(85日)以上を経過したあとの生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は健康保険の診療の対象とはなりませんので、その費用の補助という形で「出産育児一時金」が支給されます。また、女性被保険者には出産で仕事を休む間の休業補償として、「出産手当金」が支給されます。
また生まれた子どもを扶養に入れる場合は手続きが必要です。
夫婦共働きの場合、生まれた子どもは原則として収入の多い方の被扶養者となります。配偶者の扶養に入れるときは、信越化学健康保険組合への届出は不要です。
女性被保険者が出産したとき
〈出産育児一時金〉
1児につき500,000円支給されます(ただし、産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合は488,000円)。妊娠4カ月以後の出産であれば、生産か死産かは問いません。
<参考> 産科医療補償制度サイト (産科医療補償制度に加入している分娩機関の検索もできます)
〈出産手当金〉
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産日後56日までの間で、欠勤1日につき標準報酬日額(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均し30日で除した額)の3分の2相当額が支給されます。出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。出産手当金の額より少ない額の給料を受けている場合は、その差額が支給されます。
〈産前産後休業中・育児休業中の保険料免除〉
産前産後休業中・育児休業期間中の健康保険の保険料は、事業主が健康保険組合へ申し出ることにより、保険料(被保険者・事業主両方の負担)が免除されます。
被扶養者が出産したとき
〈家族出産育児一時金〉
1児につき500,000円支給されます(ただし、産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合は488,000円)。妊娠4カ月以後の出産であれば、生産か死産かは問いません。
<参考> 産科医療補償制度サイト (産科医療補償制度に加入している分娩機関の検索もできます)
出産費用の窓口負担を軽減する
「直接支払制度」、「受取代理制度」
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。
直接支払制度
出産する医療機関で手続き(被保険者が出産予定の医療機関と支給申請及び受取の代理契約を締結する)を行うことにより、健康保険組合から出産育児一時金を直接医療機関へ支払うことができる制度です。被保険者・被扶養者ともに利用できます。出産費用が出産育児一時金・家族出産育児一時金の額を超えた場合は、超えた分のみを医療機関等へお支払いください。出産費用が出産育児一時金・家族出産育児一時金の額を下回る場合の差額分は、出産後に健康保険組合から被保険者に支払われます。
※医療機関によっては直接支払制度を利用できないこともあります。
出産費用が出産育児一時金・家族出産育児一時金の額を下回る場合は、「出産育児一時金内払金(差額)支払依頼書」に、医療機関から交付された出産費用の領収・明細書の写し・医療機関と取り交わす直接支払制度を利用する合意書の写しを添えて提出 申請書
受取代理制度
受取代理制度は出産育児一時金を分娩機関が被保険者に代わって受け取る制度(出産予定の分娩機関を受取代理人とする申請書をあらかじめ、健康保険組合に提出することによって出産費から出産育児一時金を差し引いた額で済むようになる)のことです。被保険者・被扶養者ともに利用できます。受取代理制度を利用できる分娩機関は、厚生労働省へ届出を行った一部の機関に限られます。